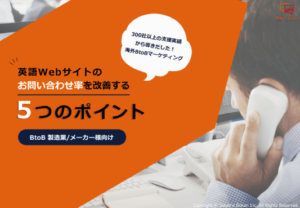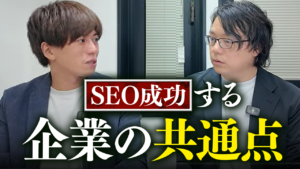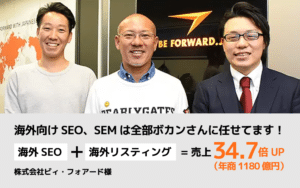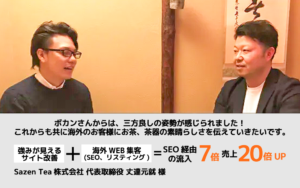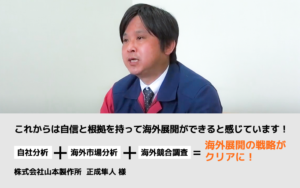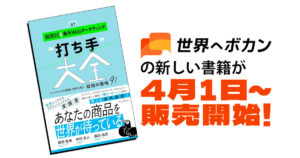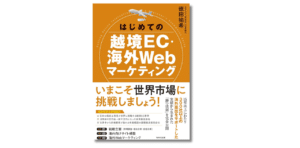お知らせ
ECの今と未来:グローバル市場動向、日本の課題、技術革新と消費者行動、物流・決済の進化
- 2023.06.05
- セミナー

ECの今と未来:グローバル市場動向、日本の課題、技術革新と消費者行動、物流・決済の進化
EC(電子商取引)は今や私たちの生活に深く根付いています。日用品から高級品まで、クリックひとつで世界中から買える便利な時代です。では、このEC業界は今どのような状況にあり、これからどこへ向かっていくのでしょうか?本記事では「ECの今と未来」をテーマに、5つの観点から最新動向をひも解いてみます。
1. グローバルECの市場動向
世界のEC市場は年々成長を続けています。2023年のEC小売売上高は約5.8兆ドルに達し、世界全体の小売売上の約19%を占めました。2029年にはオンラインで買い物をする人が36億人、つまり世界人口の約半分に達する見通しです。国境を越えたオンライン取引(越境EC)も急拡大しており、BtoC型の越境EC市場規模は2030年までに7.9兆ドル(約1,164兆円)に達するとの予測が出ています。この成長を牽引するのは中国と米国で、両国で世界EC売上の約7割を占めるとも報告されています。
グローバル企業ではAmazon(アマゾン)の存在感が突出しています。世界最大の顧客基盤と充実した物流網を持ち、特にアメリカ市場で圧倒的なシェアを誇るECの巨人です。自社物流サービス(FBA:Fulfillment by Amazon)により在庫管理から配送まで一貫対応できるため、迅速な配送と安定したサービスを実現し、消費者も出店者もその恩恵を受けています。一方でShopify(ショッピファイ)のようなプラットフォームも普及しました。Shopifyを使えば企業や個人が独自のオンラインストアを構築しやすく、世界に向け直接販売できます。言わばAmazonという巨大モールに出店するのに対し、Shopifyでは自分のブティックを開く感覚です。前者は莫大な集客力が魅力ですが手数料も高めで、後者は初期構築に時間と費用がかかる反面、デザインや機能の自由度が高く柔軟な運営が可能です。Amazonは手数料負担がある代わりにFBAで運営負荷を軽減し、Shopifyは自力での集客が必要な反面ブランド戦略を自在に展開できる、といった違いがあります。こうしたサービスの登場により、中小企業でも簡単に越境ECに乗り出せる時代になりました。実際、中国発の格安通販Shein(シーイン)や米国向けマーケットプレイスTemu(ティーム)など、新興の越境EC企業も台頭し、世界中の消費者を獲得しています。グローバルEC市場は大企業から新興企業まで競争が激しく、“ボーダレス”な買い物体験が加速しています。
2. 日本国内のEC市場と今後の課題
日本のEC市場も拡大傾向にあります。2023年の国内BtoC-EC市場規模は約24.8兆円に達し、前年から2.1兆円増(前年比9.2%増)という力強い成長を見せました。しかし、小売全体に占めるEC比率(EC化率)はまだ9.38%にとどまっています。裏を返せば、約9割の購買は依然として実店舗で行われているということです。言い換えれば、日本ではEC利用余地が大きく残されているとも言えます。
また、商品カテゴリーによってオンライン化の進み具合には差があります。例えば書籍や映像ソフトはネット購入が当たり前になっており、EC化率が5割を超えています。家電も約43%がオンライン経由で販売されており、物販分野の中でも特にEC化が進んだ領域です。一方で、生鮮食品や日用品などはまだネット販売が数%程度に留まっています。衣類・ファッション分野も2023年時点でEC化率22.88%と一定の水準にはありますが、依然として全体の4分の1に満たないのが現状です。このように、商品によってオンライン化の度合いに差があり、今後は食料品や生活必需品分野でのEC拡大が課題となるでしょう。
消費者層別に見ても、高齢者層への浸透が一つの課題です。日本は超高齢化社会であり、インターネット人口普及率は2022年時点で84.9%と高水準ながら、裏を返せば未だ国民の1割強は非インターネット層です。スマートフォンやPCの操作に慣れない高齢者がECの利便性から取り残されないようにする取り組み(UIの簡素化、サポート体制など)や、デジタルデバイド解消への対策も求められています。
地方のビジネスに目を向けると、中小店舗のデジタルトランスフォーメーション(DX)の遅れも指摘されています。大都市圏では多くの小売店がネットショップを開設していますが、地方では人手やノウハウ不足からオンライン進出できていない事例も少なくありません。EC普及により地元商店の売上が地域外の大手ECに流出してしまうと、地域経済の空洞化を招く懸念もあります。そのため各地で地元商店のネット活用支援や、ECと地域連携による地方創生の模索が進められています。
一方で、物流インフラへの負荷も深刻です。EC利用拡大に伴い、日本国内の宅配便取扱個数は年々増加しています。2022年度の宅配便取扱個数は約50億個に上り、2009年度(約31億個)と比べて約60%も増加しました。物量の急増に対応するため、宅配各社は拠点の自動化や配達効率の向上に努めていますが、ドライバー不足は慢性化しています。特に2024年から施行される働き方改革関連法による「物流の2024年問題」が懸念され、長時間労働規制の強化によって輸送キャパシティの制約が予想されています。実際、近年は燃料費や人件費の高騰もあって大手宅配3社の取扱個数は伸び悩み、一部では配達単価の値上げも起きています。こうした状況はEC事業者にも影響を及ぼし、特に地方や離島への配送コストやスピード確保が課題となっています。
もっとも、課題解決に向けた動きも始まっています。たとえば受取手段では、留守でも荷物を受け取れる「置き配」や宅配ロッカーの普及により再配達率は徐々に改善しています。(2019年から2023年にかけて、都市部の再配達率は16.6%から12.1%まで低下しました。)また、実店舗受け取りサービス(BOPIS)の拡大や、EC各社が独自の配送網(自社便や提携地域運送会社)を整備するといった取り組みも進んでいます。こうした努力を積み重ね、物流の持続可能性を高めることが日本のEC市場拡大の土台となるでしょう。
総じて、日本のEC市場は潜在力を秘めつつも、裾野を広げるための課題が存在しています。高齢者・地方への浸透、物流インフラ強化、そして中小事業者のDX推進など課題は多岐にわたりますが、これらを克服できれば日本のECはさらに飛躍できるはずです。
3. テクノロジーの進化(AI、AR、Web3、ライブコマースなど)
急成長するEC業界を支えるのが最先端のテクノロジーです。昨今はAIやARといった技術が通販体験を革新しつつあり、Web3やライブコマースのような新潮流も登場しています。
AI(人工知能)の活用はますます重要な役割を果たしています。皆さんもECサイトで「おすすめ商品」が表示されるのを目にするでしょう。それは高度化したAIのレコメンドエンジンが、ユーザーごとの閲覧履歴や購買データを分析し、一人ひとりに最適な商品を提案しているのです。まるで有能な店員が自分の好みを理解して商品を勧めてくれているかのようです。これにより消費者は埋もれていたお気に入り商品を見つけやすくなり、EC事業者側も購入率の向上につなげています。さらに、AIを搭載したチャットボットによる24時間対応のカスタマーサポートも一般化しました。チャット画面で質問すれば即座にAIが回答し、商品の詳細説明や注文状況の確認まで行ってくれます。多言語の自動応対も可能なため、海外の顧客とのやり取りもスムーズです。裏側では需要予測AIが在庫管理を最適化し、売れすぎて商品が足りなくなったり、売れ残りが発生したりするリスクを減らしています。AIが影の立役者となり、EC運営の効率と精度を飛躍的に高めているのです。難解な仕組みですが、要するに「適材適所」でAIが働き、人は創造的な部分に注力できる環境が整いつつあると言えるでしょう。
AR(拡張現実)技術もオンラインショッピングに新たな価値をもたらしています。ネット通販では実物を手に取れないという悩みが常につきまといましたが、ARを活用することでそのギャップを埋めつつあります。例えばスマートフォンのカメラを通じて、自宅の部屋に仮想の家具を配置しサイズ感や雰囲気を確かめたり、画面上の自分(またはモデル)の姿に洋服をバーチャル試着してフィット感を見ることができます。まさに「試着室やショールームを自宅に持ってくる」ような体験です。これにより購入前の不安が軽減され、返品率の低下や購買決定までの時間短縮にもつながっています。ARメイクアプリで口紅の色味を自撮り映像にリアルタイム適用して選ぶ、といったことも可能になっており、コスメやファッション分野でも広がりを見せています。今後はARグラスの普及などにより、より自然な形で仮想試着・商品確認ができるようになるかもしれません。
近年大きく注目されているのがライブコマース(ライブ配信通販)です。ライブコマースとは、販売者がリアルタイムの動画配信を通じて商品を紹介し、視聴者は配信を見ながらその場で質問したり購入できる仕組みです。テレビのショッピング番組を、双方向でインターネット上に実現したもの、と言えばイメージしやすいでしょう。配信者(インフルエンサー)と視聴者がコメント機能でコミュニケーションを取り、疑問点をその場で解消しながら購買に至るケースが多く見られます。このため従来のECよりも購入までのプロセスを短縮できる点も魅力です。ライブコマースは中国や東南アジアで爆発的に成功を収めており、人気配信者が紹介した商品が数分で何万個も売れるような事例も生まれています。例えば中国のあるトップ配信者は、わずか数十分のライブ配信で数億円相当のコスメを売り上げたことが報じられています。こうした成功を受け、欧米や日本の市場でもライブコマースの波が押し寄せつつあります。リアルタイム配信の熱気がそのまま購買意欲に直結するライブコマースは、今後ECの主要チャネルの一つになる可能性が十分にあるでしょう。
また、ボイスコマース(音声EC)も徐々に広がりを見せています。ボイスコマースとは、スマートスピーカーやスマホの音声アシスタント(Amazon Alexa、Googleアシスタント、Siri等)に話しかけるだけで商品検索・注文ができる仕組みです。例えば「アレクサ、洗剤を注文して」と声に出せば、それだけで必要な洗剤のオンライン注文が完了します。手を使わずに買い物できるため、家事育児で手が離せない時や高齢者にも便利です。まさに“話すだけでお買い物”という未来が現実になりつつあります。ボイスコマース市場は急成長しており、2025年には世界で400億ドル超規模に達するとの予測もあります。音声認識の精度向上に伴い、より複雑な注文や個人の嗜好に合わせた音声ショッピング体験が可能になるでしょう。
さらに先を見据えると、Web3やメタバースといった新潮流もECの未来を形作ろうとしています。Web3とはブロックチェーン技術を基盤とした次世代の分散型インターネットのことで、巨大プラットフォームを介さずユーザー主導でデータ管理や取引ができるのが特徴です。EC分野でもWeb3を活用した実験が始まっており、その一つがNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)の活用です。NFTはデジタルデータに唯一無二の所有証明を与える技術ですが、これを使って「トークン保有者限定」の販売や特典提供を行う動きが出てきました。例えば、特定のNFTをウォレットに保有している顧客だけがアクセスできる限定セールや特別コミュニティを用意するといったトークンゲートコマースです。実際、ShopifyはNFTを使った新しいEC機能を提供し始めており、NFT保有者に限定商品の購入権を与えたり、ブランドのファンコミュニティを強化する施策が可能になっています。デジタル会員証とも言えるNFTを配布し、所有者に割引や先行販売といった特典を付与することで、ブランドへのロイヤルティを高める試みが進んでいるのです。
一方、メタバース(仮想空間)もECの新たなフロンティアです。企業はメタバース上にバーチャル店舗を構築し、ユーザーはアバター(分身キャラクター)を操作してその店内を自由に歩き回り、商品を手に取るように閲覧・購入できる環境づくりを進めています。例えばアパレルブランドが仮想店舗を開き、ユーザーは自分のアバターに服を着せて試着体験を楽しみ、そのまま購入できる──そんな取り組みが現実化しつつあります。また、家具や家電など高額商品の分野でも、メタバース上の仮想空間に商品を配置してサイズ感やデザインを確認できるサービスが登場しています。メタバースでは国や物理的距離を超えてユーザー同士が集まれるため、ブランド主催の仮想イベントでファン同士が交流したり、限定商品の販売会を開いたりとコミュニティ形成にも活用されています。決済や物流の仕組みが整えば、将来的にはメタバース内で見た商品が現実世界に届けられる、というシームレスな購買体験も実現するかもしれません。
このように、テクノロジーの進化はECに次々と新しい風を吹き込んでいます。AIが裏方を支え、ARやVR(仮想現実)、メタバースが体験をリッチにし、Web3がこれまでにない顧客参加型のモデルをもたらそうとしています。ライブコマースやボイスコマースは従来のショッピングの常識を覆しつつあります。今後もテクノロジーの進歩とともに、ECの形はダイナミックに変化していくでしょう。
4. 消費者行動の変化(Z世代、モバイルシフトなど)
テクノロジーと並んで、消費者行動の変化もECの今と未来を語る上で欠かせない要素です。特に台頭しているのがZ世代と呼ばれる若年層の存在です。1990年代後半〜2010年代生まれのZ世代は、生まれた時からインターネットやスマホが身近にあったデジタルネイティブ世代です。彼らの消費行動にはいくつかの特徴があります。
まず、モバイルシフトです。若い世代ほどPCではなくスマートフォンで買い物を済ませる傾向が顕著になっています。日本でもネット利用デバイスはPCからスマホ中心へと移行し、2022年時点で世帯のスマホ保有率は90.1%に達しパソコン保有率(69.0%)を大きく上回りました。通勤通学の電車内やちょっとしたスキマ時間にスマホでサッと買い物することが当たり前になりつつあります。実際、世界的に見てもモバイル経由のEC取引は主流化しており、ある調査ではマレーシアでは国民の約45%が週に1回以上スマホでオンラインショッピングを利用していると報告されています。このように「いつでもどこでも」スマホさえあれば買い物できる環境が整ったことで、消費者は時間や場所に縛られず購買行動を取るようになりました。EC事業者側もモバイルファーストを掲げ、スマホで見やすく操作しやすいサイト構築や決済フローの最適化に力を入れています。
次に、SNS(ソーシャルメディア)の影響力が飛躍的に増しています。Z世代を中心に、情報収集から商品の発見までSNSが欠かせないツールとなりました。例えばInstagramで友人が紹介していたコスメをそのまま購入したり、TikTokの動画で見かけたガジェットが欲しくなって公式サイトに飛ぶ、といった行動は珍しくありません。実際、Z世代のEC購買行動ではSNS経由での商品購入が非常に多いことが調査で明らかになっています。彼らはTwitterやInstagram、YouTube、TikTokといったプラットフォームを自在に使いこなし、そこでキャッチした情報から商品価値を判断して購入を決める傾向が強いのです。言い換えれば、「誰が言うか」が重要で、企業の一方的な広告よりも、共感できる個人(インフルエンサーやYouTuber、あるいは友人)の発信内容が購買意欲を刺激します。このため企業側もSNS上でのUGC(ユーザー生成コンテンツ)に注目しています。実際にユーザーが投稿した口コミ写真やレビューは他の消費者に大きな影響を与えるため、企業もUGCを通じた自然な商品の訴求を促す戦略をとり始めています。例えば、ハッシュタグキャンペーンで消費者に商品写真を投稿してもらったり、SNS映えするパッケージデザインにしてシェアを促すなど、SNS時代ならではのマーケティングが展開されています。
Z世代の価値観も特徴的です。彼らは多様性や社会課題への関心が強く、購入するブランドや商品の背景にも敏感です。単に安い・便利というだけでなく、「このブランドの理念に共感できるか」「サステナブル(持続可能)な取り組みをしているか」などを重視する傾向があります。例えば環境意識が高く、使い捨てではなくリユース(中古品)の利用に抵抗が少ないこともZ世代の特徴です。実際、古着やリセール(再販)市場の成長はZ世代の支持に支えられており、ファッションECでも中古品を扱うプラットフォームが人気を博しています。またZ世代は非常に情報収集能力が高く、購買に際して入念にリサーチを行います。一方で「推し」文化とも親和性が高く、いったんこのブランドが好き!とハマると熱狂的に支持しリピートする傾向もあります。
要するに、自分にとって価値があるかを見極めた上で、お気に入りにはとことん入れ込むというメリハリのある消費スタイルです。企業にとっては、Z世代に響く世界観やストーリーを発信し、共感を得ることがファン獲得の鍵となっています。「これは自分のライフスタイルに合っている」「このブランドを応援したい」と思ってもらえれば、Z世代は喜んでそのブランドの宣伝者にもなってくれるでしょう。
さらに、オムニチャネル(チャネル横断型)の購買行動も一般化しました。消費者はオンラインとオフライン、どちらか一方ではなく状況に応じて両方を使い分けています。例えば、店舗で実物を確認してから家に帰ってネットで購入したり、逆にネットで下調べした商品を実店舗で試着・体験してから買うといった流れです。オンラインとオフラインの境界が曖昧になりつつある今、企業側も統合的な顧客体験を提供する必要があります。実店舗とECサイトの在庫情報を連携させたり、店舗受け取りや店舗返品を可能にするなど、チャネルを跨いでもストレスなく買い物できる環境づくりが求められています。例えばユニクロなどは店舗とオンラインストアの在庫を共有し、オンラインで注文して店舗で受け取れるサービスを展開しています。このように「どこで買っても同じように便利」な体験こそ、現代の消費者が望むものなのです。
このように、デジタル世代の登場とライフスタイルの変化により、消費者の購買行動は大きく様変わりしています。EC企業はその変化に迅速に対応し、新しいニーズに応える必要があります。逆に言えば、消費者行動のトレンドを的確に捉えた企業が次世代のEC市場をリードしていくことでしょう。
5. ECにおける物流や決済の進化
最後に、物流と決済の進化についてです。これらはECの裏側を支える重要な要素であり、近年めざましい革新が起きています。
物流の進化と課題克服
まず物流(ロジスティクス)の面では、近年は配送スピード競争が激化しました。Amazonがプライム会員向けに当日~翌日配送を当たり前にしたことで、消費者も「ネット注文すればすぐ届くもの」と期待するようになっています。配送の迅速化と送料無料サービスの広がりに対応するため、各EC事業者は物流拠点を増やし、在庫を消費地に近い場所に置く工夫をしています。倉庫内では自動化・ロボット化が進み、人手を介さずロボットが棚から商品を取り出して仕分けするシステムを導入する企業もあります。これにより大量の注文にもスピーディーに対応し、人的コストの削減にもつなげています。
配送手段にも革新の波が押し寄せています。都市部では自動配送ロボットが歩道を走り宅配する実証実験や、ドローン配送のテストが行われ始めました。将来的には、人手を介さないラストマイル配送が一部で実現する可能性があります。また、ユニークな取り組みとして、高速道路の路肩に自動運転トラック専用レーンを設ける構想も検討されています。これは深刻化するドライバー不足をテクノロジーで補い、長距離輸送を省人化しようという試みです。現時点では構想段階ですが、物流業界は未来志向でさまざまなアイデアを模索しています。
こうした技術革新に加え、既存の配送網の運用改善も進んでいます。先に触れた「2024年問題」に対応するため、トラックドライバーの労働環境改善や配送効率化が急務となっています。その一環として普及が加速しているのが共同配送や地域拠点受け取りといったモデルです。複数のEC企業が宅配便業者を共有したり、地域の商店や施設が受け取り拠点となって住民に荷物を渡す仕組みを整えたりすることで、一件一件個別に届ける非効率を解消しようという動きです。また、ラストワンマイルにおける工夫として、前述の置き配(玄関先等に非対面で配達)や宅配ロッカーの活用が定着しつつあります。これらにより再配達が減り、配達員一人あたりが配れる件数を増やすことができています。2019年から2023年にかけて、都市部の再配達率が16.6%から12.1%に低下するなど改善が見られたのは、置き配・宅配ボックスの浸透やコロナ禍での在宅率向上が背景にあります。今後もこれらの施策を推進し、効率的かつ持続可能な物流体制を作ることがEC業界全体の課題となっています。
決済の進化と多様化
次に決済の進化です。ECにおける支払い手段は、この十数年で飛躍的に多様化・便利化しました。かつてオンライン決済と言えばクレジットカードか代引き(代金引換)ぐらいでしたが、今や電子マネー、スマホ決済、後払いサービスなど選択肢は豊富です。
特に近年目覚ましいのが、スマートフォンを使ったキャッシュレス決済の普及です。日本政府もキャッシュレス化を推進しており、2025年までに決済の40%をキャッシュレスにする目標を掲げていました。それに対し、2024年時点で日本のキャッシュレス決済比率は42.8%に達し、目標を前倒しで達成したと報告されています。これは、クレジットカードはもちろん、QRコード決済や電子マネーといったスマホ決済が広く浸透した結果です。内訳を見ると、クレジットカードが依然最大のシェアを占めますが、近年コード決済(バーコード・QRコードによるスマホ決済)が急伸しています。例えばスマホ決済サービスのPayPayは利用者と加盟店を急速に増やし、2024年には国内キャッシュレス決済全体の取引回数の約5回に1回がPayPay経由になったとも報告されています。街のお店でも「PayPay使えます」の貼り紙を見かける機会が増えたのではないでしょうか。ECサイトでも、クレジットカード番号を直接入力せずとも、スマホのウォレットアプリでスムーズに支払える仕組みが当たり前になりました。
決済手段の多様化も顕著です。クレジットカード一強の時代から、デビットカード、プリペイド決済、電子マネー(交通系ICや流通系ICなど)、さらにはBNPL(Buy Now Pay Later)と呼ばれる後払い決済サービスまで、多彩なオプションがあります。BNPLは商品を受け取った後に分割払いなどで代金を支払う方式で、煩雑な審査なく利用できる手軽さから若者を中心に利用が広がっています。クレジットカードを持たない・使いたくない層でも分割払いができるため、「今すぐ手元に欲しい」を後押しする新たな支払い手段として注目されています。実際、国内でもPaidy(ペイディ)などのBNPLサービスが普及し、大手ECサイトにも後払いオプションとして導入されています。ただし、分割払いによる債務超過リスクや若年層の過剰利用といった課題も指摘されており、適切な審査・利用限度の設定など業界でルール整備が進められています。
さらに、セキュリティと利便性の両立も決済分野の重要テーマです。オンライン決済が主流になるにつれ、不正利用や情報漏洩への不安も高まりました。その対策として、近年は多要素認証(例:パスワード+SMSコード)や生体認証決済(指紋や顔認証での支払い)が取り入れられ、安全性を高めています。例えばApple PayやGoogle Payでは、生体認証を通過しないと決済が完了しない仕組みで不正を防止しています。一方で手続きは極めてスムーズで、ユーザーは端末に指を触れるだけ・顔を向けるだけで支払いが完結します。つまりセキュリティ強化とユーザー体験向上を両立させる方向に進化しているのです。
なお、一部には暗号資産(仮想通貨)決済を導入するECサイトも出てきました。ビットコインやイーサリアムで商品購入ができる例もあります。ただ価格変動リスクなどもあり、現状ではごく一部の先進的な試みと言えるでしょう。しかし将来的に各国のデジタル通貨(CBDC)や安定したステーブルコインなどが普及すれば、国境を越えたスムーズな決済手段としてECに組み込まれる可能性もあります。決済手段はまさに技術革新とユーザーニーズに合わせて進化を続けている最中です。
ECの今と未来まとめ
以上、「ECの今と未来」をグローバル市場、日本国内、市場を支える技術、消費者の動向、物流・決済の観点から見てきました。絶えず変化するEC業界ですが、その根底にあるのは便利さの追求と新しい価値体験の創造です。世界中どこからでも欲しい物が手に入り、AIやSNSの力で自分好みの商品と出会える。そしてリアルとバーチャルの垣根が溶け合い、買い物自体がエンターテインメントになっていく。そんな未来がすぐそこまで来ています。
この急速な進化の中で、私たち消費者も柔軟に楽しみながら適応していきたいものです。例えば、昔は抵抗があったネット決済も、今では当たり前のように使いこなしている人が多いでしょう。同じように、新しいショッピング体験もまずは試してみることが大切です。ライブコマースでコメントを送ってみる、ARアプリで家具を配置してみる、スマホ決済でスイスイ会計を済ませる──便利さを享受しつつ、自分に合ったスタイルを選べば良いのです。
ECの未来は、不確実でありながらもワクワクする方向に進んでいます。オンラインとオフライン、人とAI、現実世界と仮想世界が融合し、今よりもっと快適で楽しい買い物ができるようになるでしょう。技術が進んでも最後に物を買うのは私たち人間です。便利さと同時に、人の心を満たすような温かみのあるサービスが求められることも変わりません。これから先、ECはどんな進化を遂げていくのか――消費者としてもビジネス従事者としても、その行方を注視しながら、新しい潮流を積極的に取り入れていきたいですね。あなたは、この変化についていけそうでしょうか?
ECの今と未来 COLOR ME SHOP DAY 2023
6月7日(水)、8日(木)開催予定のカラーミーショップ様主催「COLOR ME SHOP DAY 2023」に弊社代表・徳田が登壇いたします!こちらは無料のオンラインイベントとなります。
7日12:20~13:15に、「越境EC成功の秘訣は?国境を超えた商品販売のための成功戦略」というテーマでお話させて頂きます。
イベントの詳細、お申込みについてはこちらから
https://shop-pro.jp/news/202306-colormeshopday/
セミナー詳細
インバウンド需要が回復傾向にある今、なぜ「越境EC」への注目は続いているのでしょうか。実際に海外向けの販売を行っている事業者さまのリアルな声や課題を取り上げながら、2023年現在の越境EC市場のトレンドや、今後予測される未来などについて専門家とともに考えます。
主な内容
- 越境ECが注目されるようになった背景
- コロナ収束後も続く越境ECへの需要
- 事業者が抱える越境ECの課題
- 2023年のトレンドと今後の変化予測
登壇者
GMOペパボ株式会社 カラーミーショップ マネージャー 和田 真人氏
世界へボカン株式会社 代表取締役 徳田 祐希
海外マーケの実践的なノウハウを無料配信中!
「海外売上を伸ばしたいけど…、なかなかうまくいかない…。」
そんなお悩み、ありませんか?
越境ECや英語SEO、広告運用、市場調査などの実践的なノウハウを無料メールマガジンで配信中!